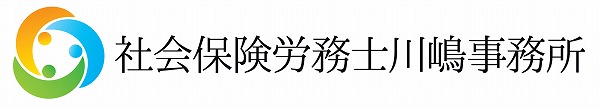労働者が会社を辞める際というのは、労使間でトラブルが起きやすいタイミングでもあります。
会社にいるときは「会社のためなら仕方ない」「給与をもらってるから仕方ない」と思っていたとしても、会社を辞めるとなると、そういった歯止めがなくなるからです。
こうした退職時のトラブルを避けるためにも、就業規則において退職に関する規定をきちんと整えておきたいところです。
- 就業規則に「退職」条文を定める必要性と、法律上の位置づけ
- 退職理由(合意退職・辞職・自然退職など)をどこまで細分化すべきか
- 退職の申出期限や、退職届・退職願の違いと実務上の注意点
- 退職時トラブルを防ぐための就業規則「退職」条文の具体的な規定例
法律・労務管理から見た「退職」
この記事は、退職と就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見た退職について、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。

「退職」条文の必要性
退職については、就業規則の絶対的必要記載事項に当たるため、就業規則への定めは必須です。
ここでいう退職とは「任意退職、解雇、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項」をいいます。
本記事最後の規定例では「退職」「退職の手続き」「退職証明」の条文を上げています。
このうち「退職」「退職の手続き」については確実に定めが必要と考えられますが、「退職証明」については微妙なところで、実際、記載がない規定例もみられます。
「退職」条文作成のポイント
退職の種類により、どこまで条文を細分化すべきか
合意退職や定年、解雇のように退職事由には様々なものがあります。
そのため、就業規則では退職の種類ごとに条文を分けるのが一般的です。ただ、どの程度の細かさで分けるかは規定例によって異なります。
この記事の最後の規定例では、解雇と定年は別規定とし、それ以外の「合意退職」「辞職」「自然退職」は「退職」にまとめるという、比較的オーソドックスな形を取っています。
合意退職と辞職とで、退職時の扱いを分けたい場合
法律の条文上は、会社の合意なく労働者は辞められる、といっても、そこは会社だって人間です。
例えば、退職金を支給している会社の場合、円満に退職した人と、勝手に辞めていった人とで同じ基準で退職金を払いたくない、というのは人情でしょう。
そして、重要なのは、このように退職理由によって、退職金に差を設けたり、あるいは他の制度で差を設けることは、法律に違反しない限りは問題ありません。
よって、退職理由で退職までや退職後の扱いを法令に違反しない範囲で差を設けたい、という場合は、合意退職と辞職が、全く別の物であることがわかるように規定しておくのがオススメです。
正社員の退職事由であるなら契約期間満了は不要
退職事由の一つである契約期間の満了ですが、基本的に正社員の就業規則には不要です。
多くの会社は正社員をフルタイムの無期雇用で雇用しているからです。
正規と非正規の違いがあやふやだと同一労働同一賃金上問題があるので、正規には有期雇用の労働者はいないことをはっきりさせるためにも、記載は避けた方がよいでしょう。
逆に、正社員であっても期間雇用という場合、契約期間の満了を退職事由として定めておく必要があります。
行方不明時の対応
就業規則に「従業員が行方不明となり、連絡が取れない期間が継続して○日に達したとき」を退職事由として定めることは割と一般的です。
こうした規定が果たして有効なのか、という点は専門家のあいだでも考えが分かれるところですが、行方不明になった労働者が戻ってくることはまずないので、あまり問題となることはありません。
なお、「連絡が取れない期間が継続して○日」という部分については、本人からの意思表示がないため辞職のように「14日(2週間)」とするのは短すぎると考えられます。
どの程度が妥当かは判断が難しいですが、最低限1か月以上は必要ということで、記事の最後の規定例ではここの日数を「30日」としています。
退職の申出期限
退職の申出期限は合意退職のときのみ有効です。
なので、労働者側が合意してくれる分には、どんな期間でも定めることができます。
ただ、この期間があまりに長すぎると「だったら2週間で辞職する」となりかねません。常識の範囲内で定めるべきといえるでしょう。
一方で、退職の申出期限を辞職の効力が発生する「2週間」と同じにしてしまうと、そもそも合意退職を行う意味が薄れてしまいますが、それでも問題がないという場合はそれで構いません。
労働者に提出させるのは退職届か退職願か
退職の手続きにおいて、退職届を出させるのか、退職願を出させるのかは、細かい部分ですが大きな違いがあります。
退職届とは、退職の意思表示であり、一度出したら撤回はできません。
一方、退職願は、会社への労働者からのお願いですので、会社がそれに同意しないと効力がない分、同意する前であれば、労働者からの撤回は可能です。
どちらがいいかは考え方次第ですが、基本的には、後になって「退職を撤回したい」などの辞める辞めないの問題が発生しにくい(仮に労働者がそう言ってきたとしてもはねのけられる)退職届を出させる方が良いかと考えられます。
会社が貸したものを労働者に返させるための定めをしておく
労働基準法には、労働者から借りたものを会社に返させたり、弁済させる義務は定められていますが、その逆はありません。
そのため、就業規則には、会社が貸してるもの等を、退職時に労働者に返させる・弁済させる規定を定めておくべきといえます。
もちろん、こうした規定がなくても返させること自体は可能ですが、就業規則に定め周知する方が、効力は高いと考えられるからです。
定年と解雇は別規定で
退職事由のうち、定年と解雇については基本的に別規定に定めます。
なお、定年と解雇の詳細について別規定に定める場合も、退職事由としてこの2つを入れる規定例がありますが、これについては完全に好みなので、どちらでも構いません。
就業規則「退職」の規定例
第○条(退職)
従業員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、翌日に従業員の身分を失う。
① 本人が死亡したとき
② 従業員が自己都合による退職を願い出て、会社がその承認をしたとき
③ 前号の承認なく、退職届の提出後14日を経過したとき
④ 休職期間が満了し、復職できないとき
⑤ 従業員が行方不明となり、連絡が取れない期間が継続して30日に達したとき
⑥ 当社の役員に就任したとき(ここでいう、役員とは会社法上の役員のみを指し、兼務役員等は除く)
⑦ その他、退職について労使双方で合意したとき
第△条(退職の手続き)
- 自己都合により退職する従業員は、30日前までに退職届を文書で提出し、承認あるまで従前の職務に服さなければならない。
- 前項の退職届を会社が受理したとき、会社は従業員の退職を承認したとものとみなす。承認後は原則、従業員は退職の意思を撤回することはできない。
- 自己都合により退職する従業員は、業務の引継ぎを完了させ、重要な事項を会社に報告しなければならない。
- 退職事由にかかわらず、退職する従業員は、退職日までに、健康保険証、その他会社からの貸付金品、会社に対する債務、または自らが管理していた会社および取引先等に関するデータ・情報書類等を直ちに返納、あるいは弁済しなければならない。
第□条(退職証明)
- 会社は、退職または解雇された者が、退職証明書の交付を願い出た場合は、すみやかにこれを交付する。
- 前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金および退職の理由とし、本人からの請求事項のみを証明する。
- 解雇の場合であって、当該従業員から解雇理由について請求があったときは、解雇予告から退職日までの期間であっても1項の証明書を交付する。
規定の変更例
退職について細かく分ける場合
第○条(合意退職)
1 従業員が退職希望日の30日以上前に、退職の申出をした場合、会社はこれを承諾する。
2 前項にかかわらず、退職の申出が退職希望日の30日以上前でない場合であっても、会社はその申出を承諾することができる。
第△条(辞職)
1 従業員の退職の申出に対し、会社が承諾しない場合、その申出から2週間を経過した時点で労働契約は終了するものとする。
2 従業員が労使双方の合意の有無にかかわらず、2週間以内の退職を望む場合、その旨を退職届に記載した上で、その申出を行う必要がある。前項の申出について、従業員はこれを撤回することはできない。
第□条(自然退職)
従業員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、翌日に従業員の身分を失う。
① 本人が死亡したとき
② 休職期間が満了し、復職できないとき
③ 従業員が行方不明となり、連絡が取れない期間が継続して30日に達したと
④ 当社の役員に就任したとき(ここでいう役員とは会社法上の役員のみを指し、従業員としての身分を残す場合を除く)
▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)
社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、就業規則の作成・改定を行っています。川嶋事務所では、この記事で見た条文を含め、
・会社の実態に合った規程設計
・法改正を見据えたルール作り
・将来のトラブルを防ぐ条文設計
を重視し、あなたの会社に合った就業規則を作成します。