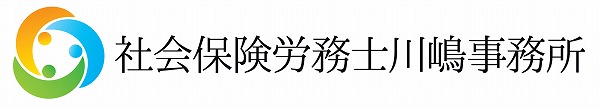フレックスタイム制は労働者に人気のある働き方である一方、その内容は「出社時間を自由に決められる制度」といった、表面的な理解にとどまっているケースも少なくありません。
実際には、会社がフレックスタイム制を導入しようとする場合、労働時間の考え方や制度上の前提を理解する必要があるほか、会社の業種や業務内容によっては、必ずしも適していない場合もあります。
また、そもそも制度のメリットだけに注目して導入を検討すると、運用の段階で思わぬトラブルが生じることもあります。
この記事では、フレックスタイム制の基本的な仕組みを整理したうえで、メリット・デメリットや、向いている会社・向いていない会社の特徴について解説します。
- フレックスタイム制の基本的な仕組み
- フレックスタイム制の主なメリット
- フレックスタイム制のデメリットや注意点
- フレックスタイム制が向いている会社・向いていない会社の特徴
- 導入や運用を検討する際に、次に確認すべきポイント
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、始業と終業の時刻を労働者の決定に委ねるというものです。
例えば、午前8時に来て午後5時に帰ったり、午後10時に来て午後7時に帰る、みたいなことを会社ではなく労働者が決めることができます。
ただし、完全に労働者の決定に任せてしまうと、夜の10時に来て朝の7時に帰る、みたいなこともできてしまいます。
そのため、フレックスタイム制を導入している会社では、「この時間からこの時間は会社に出社していてください」というコアタイムや、「この時間からこの時間のあいだで始業・終業時刻を決定してください」というフレキシブルタイムを定めるのが一般的です。
フレックスタイム制のメリット
労働者が自分の出社・退社時刻を決められる
労働者が自分の出社・退社時刻を自由に決められるのがフレックスタイム制の最大の特徴です。
これにより、例えば、小さなお子さんのいる家庭では、保育園の送り迎えが楽になったり、あるいは、夜の予定のために早めに出社して仕事を終らせる、といったように、労働者がプライベートの充実を図ることができます。
通勤時間をずらせる
労働者が個々に出社・退社時刻を決定できるため、通勤ラッシュの時間帯を避けて通勤することができます。
3ヵ月以内のあいだの繁忙期と閑散期で、労働時間を調整できる
フレックスタイム制を適用された労働者は、清算期間(※)という期間内に、会社が法定の範囲で定める総労働時間数分を、労働者が始業・終業時刻を調整しながら働きます。
例えば、1カ月の所定労働時間の総労働時間が177時間という場合、1日の労働時間が6時間になる時があってもいいし、9時間になるときもあっていい。けれども、労働者は清算期間全体を通しては、177時間は必ず働く必要がある、ということです。
よって、1カ月の期間で繁忙期と閑散期がある場合、繁忙期は長く働いて、閑散期は短く働く、ということが労働者の裁量で可能となります。
2019年4月の法改正で清算期間の上限が3ヵ月(それまでは1か月)とされたことで、より長い範囲で繁忙期・閑散期への対応ができるようになり、より柔軟な働き方ができるようになっています。
※ 清算期間:フレックスタイム制を適用する期間のこと。例えば清算期間が1ヵ月の場合、この1ヵ月の中で労働時間数を調整する。
残業代の削減に繋がる場合も
フレックスタイム制では、残業代の支払いは、1日や1週の労働時間ではなく、清算期間内の総労働時間を超えたかどうかで見ます。
どういうことかというと、例えば、清算期間が1ヶ月(暦の日数31日の月)の場合、総労働時間は以下のように
1週間の法定労働時間40時間×(変形期間の暦の日数31日÷7)=177.14
となります。
この177.14時間を超えないかぎり、1日の労働時間が8時間を超えても、1週の労働時間が40時間を超えても時間外労働は発生しません。
フレックスタイム制の場合、労働時間の決定権は労働者にあるので、労働者がきちんと調整してくれることが前提ですが、うまくいけば、通常の労働時間制よりも残業時間を減らせる可能性があります。
フレックスタイム制のデメリット
同僚や取引先との同期的な仕事が困難
メールやSNSといったIT技術の普及により、同じ時間を共有して仕事をするということは減ってはきています。
同じ時間を共有して仕事をする、というのは、直接顔を合わせたりすることや電話による連絡で、これらは相手と同じ時間に労働していないと、仕事ができません。
昔と比べて、そうした同期的な仕事や方法は減ってはきているものの、中小や地方ではまだまだそうしたコミュニケーションや取引が主流です。
しかし、フレックスタイム制では、労働者が出社・退社時刻を決めるため、そうしたやり方は難しくなります。
社員の滞在時間のバラ付きにより経費がかさむ
コアタイムである程度制限はできるとはいえ、フレックスタイム制の場合、朝早くに出社してくる労働者もいれば、昼近くになってやっと出社してくる労働者もいます。
となると、通常の労働時間制のように、みんなで同じ時間に出社して退社する場合よりも、会社内に労働者がいる時間は長くなります。
細かい話ですが、社内の同じ部屋に10人いようが1人だけだろうが、照明などの電気代は同じなため、その分、経費は増えることになります。
フレックスタイム制が向いてる会社・向いてない会社
労働者の裁量が大きい会社
フレックスタイム制は他の変形労働時間と違い、コアタイム以外、会社が労働者の労働時間を指定することができません。
つまり、労働者に労働時間の決定権を委ねる、というのがフレックスタイム制の大きな特徴です。
(このため、フレックスタイム制は厳密には変形労働時間制ではないとされています)
労働時間の決定権を委ねる、というのは、イコール働き方の決定権を委ねるのも同然。
よって、デザインや研究職といった個人で業務を行うことの多い業種や業務(デザインなど)が向いているといえます。
大企業
人的リソースに余裕のある大企業の場合、フレックスタイム制を利用しても、個々の労働者の負担がそれほど大きくなりません。
その一方で個々の労働者の働き方のニーズ、例えば、満員電車は嫌なので通勤時間を遅らせたいだとか、子どもの保育園の送り迎えをしたいといった要望をを一手に解決できることから、導入には向いているといえるでしょう。
向いてない職種等
一方で、ライン作業の工場のように、労動時間や働き方に労働者の裁量が含まれる余地がない業務での導入はオススメできません。
もちろん、飲食や小売といったお店の開店・閉店時間が決まっているような業種でも難しいでしょう。
フレックスタイム制の導入方法
フレックスタイム制の導入に当たっては就業規則の改定や労使協定の締結が必要になります。
詳しくは以下の記事をご覧ください。

フレックスタイム制の労働時間と割増賃金
フレックスタイム制は導入して終わりというのものではありません。
特に時間外労働と割増賃金については間違えやすい部分となります。
それらの詳細については以下の記事で解説していますので、こちらをご覧いただければと思います。

▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)
こちらの制度は、就業規則にどう定めるかでリスクが変わります。
制度理解だけでなく、自社に合った条文設計や運用まで落とし込むことが重要です。
「不安がある」「何していいかわからない」という方はぜひこちらを!