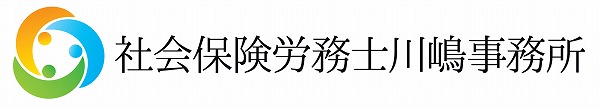- 変形労働時間制の基本的な仕組みと、法定労働時間との関係
- 4つの変形労働時間制(1か月単位・1年単位・1週間単位・フレックスタイム制)の違いと使い分け
- 変形労働時間制を適用できる労働者・できない労働者(未成年者、妊産婦、派遣社員など)の整理
- 部署別・労働者別に異なる変形労働時間制を導入できるか、その際に必要な手続き
- 期間設定(長期・短期)や届出に関する、実務でよくある疑問と注意点
変形労働時間制とは
日本の労働基準法では「1日8時間、1週間40時間」と上限となる労働時間が決まっています。
しかし、業務には繁閑がつきもの。
季節によっては、1週間40時間でも時間が足りないこともあれば、余ることもあります。
変形労働時間制とは、1ヶ月や1年間という期間内で、平均して1週間の労働時間が40時間になっていれば、余裕がある時期には労働時間を短くし、忙しい時期には労働時間を長くしてもいい、という制度です。
この制度を有効活用すれば、余計な残業や休日労働を削減し、残業代等の節約もできます。また、労働者のワーク・ライフ・バランスの向上にもつながるため、有効に活用したいところです。
4つの変形労働時間制
変形労働時間制には、以下の、それぞれ用途が異なる4つの制度があります。
1か月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1カ月の中で、労働時間を平均で週40時間以内とする制度です。
平均で週40時間なので、月曜日から土曜日の6日間、毎日8時間働かせて週48時間になったとしても、他の週の労働時間が短くなっていればOKということです。
なお、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、1か月よりも変形期間を長くすることはできませんが、短くすること可能です。
そのため、例えば、2週間単位での変形なども可能ですが、労働時間や給与の計算が複雑となるため、1か月単位での変形を採用する会社がほとんどです。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
1カ月単位の変形労働時間制とは? メリット・デメリット、導入方法を解説
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1年の中で、労働時間を平均で週40時間以内とする制度です。
1か月単位の場合、1か月という短い期間での業務の繁閑にしか対応できませんが、1年単位の変形労働時間制では、年間の繁忙期と閑散期への対応が可能です。
なお、1年単位の変形労働時間制は、変形期間を1か月超1年以内とすることができるため、例えば3か月単位や半年単位の変形期間を設けることも可能です。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
1年単位の変形労働時間制|制度の仕組み・メリットとデメリットをわかりやすく解説
1年単位の変形労働時間制の導入方法|就業規則・労使協定の整備と提出手続き
1年単位の変形労働時間制の運用|残業代計算や途中入社の清算、うるう年の注意点
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1週40時間の枠はそのまま、1日8時間の上限を10時間まで延長できる制度です。
ただし、こちらについては採用できる業種が小売業、料理店、旅館、飲食店に限られる上、規模も30人までと、採用できる事業場はかなり限られます。
より詳しい制度の解説は、以下からどうぞ。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業時刻を決定する制度です。
他制度と違い、労働時間の変形の主体が会社ではなく労働者にあるため、厳密には変形労働時間制ではない、とも言われていますが、便宜上、変形労働時間制に分類されることが多いです。
制度の詳しい解説に関しては、以下をどうぞ。
フレックスタイム制とは|制度の仕組み・メリットとデメリットをわかりやすく解説
フレックスタイム制の導入方法|就業規則・労使協定の整備と提出手続き
フレックスタイム制の労働時間と割増賃金|法定労働時間の総枠の考え方
変形労働時間制の対象者
変形労働時間制の対象者については、基本的に制限はありません。ただ、一部適用できない制度と労働者の組み合わせがあるので注意が必要です。
未成年者
15歳年度末までの児童についてはそもそも就労させることが原則不可となっています。
例外的に使用する場合も、修学時間と通算して週40時間、1日7時間までと労働時間が決まっており、変形労働時間制は利用できません。
未成年者で、15歳年度末後から満18歳未満の場合、1カ月単位と1年単位については「1日8時間、1週48時間の範囲」という制限付きで認められています。
満18歳以上のものについては、通常の労働者同様に、変形労働時間制を適用することができます。
妊産婦
妊産婦の場合、妊産婦から「請求があった場合」に限り、会社は以下の3つの変形労働時間制の適用ができません。
- 1カ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制については、会社ではなく労働者が始業時刻と終業時刻を決められるという特殊性から、妊産婦も適用除外とはされていません(むしろ、積極的な利用が推奨されています)。
ちなみに、妊産婦から請求があった場合、法定の時間外労働及び休日労働をさせることもできないため注意が必要です。
パートタイマー・アルバイト、契約社員や嘱託社員
パートやアルバイト、契約社員や嘱託社員の場合でも変形労働時間制は適用できます。
ただ、パートやアルバイトの場合、そもそも所定労働時間が通常の労働者よりも短かったり、働き方がシフト制だったりして、活用しなくても問題ない、ということも少なくありません。
派遣社員
派遣社員の場合も適用することはできますが、注意する点があります。
派遣社員が変形労働時間制を利用する場合、労使協定の締結や監督署への提出は、派遣先の企業ではなく、派遣元の企業となります。
派遣元に責任:36協定の提出、1年単位の変形労働時間制の届出、時間外手当の支払い
派遣先に責任:労働時間、休憩等の管理
そのため、派遣先の企業で変形労働時間制を利用していたとしても、派遣元で変形労働時間制を利用していない場合、派遣労働者は変形労働時間制ではなく通常の法定労動時間で業務を行い残業代計算等を行う必要があります。
例えば、派遣先は隔週土曜が出勤日だけども、1年単位の変形労働時間制を利用しているので、1日の所定労働時間については残業代は発生しない、という場合でも、派遣元で派遣先に合わせた1年単位の変形労働時間を利用していないと、この土曜日は残業代が発生する可能性があるわけです。
その他、変形労働時間制についてよくある質問
3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することは可能か
- 3年の長期の期間や半月などの短期の期間でも、変形労働時間制を利用することは可能か?
-
まず、3年などのように、1年よりも長い期間で労働時間を変形させる場合についてですが、こちらはできません。
1年単位の変形労働時間制や1箇月単位の変形労働時間制は、言い換えれば「最大1年単位の変形労働時間制」「最大1箇月単位の変形労働時間制」だからです。
そのため、質問のように、3年の長期で労働時間を変形させる場合は、1年単位の変形労働時間制を3回に分けておこなう必要があります。
一方、半月で労働時間を変形させる場合については、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間を半月に設定すれば可能です。
- 異なる部署や労働者ごとに異なる変形労働時間制を利用することは可能か?
-
変形労働時間制の最小適用範囲の定めはない
1か月単位及び1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制のいずれも、適用の最小範囲に関する定めはありません(適用範囲の最大についても記載はありませんが、労働基準法が基本的に事業場単位での適用を想定しているため、最大は事業場単位となります)。
よって、異なる部署や労働者ごとに異なる変形労働時間制を利用することは不可能ではありません。
対象労働者の範囲の明確化が必要
ただし、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制のいずれも、導入するにあたっては、労使協定(1か月単位の変形労働時間制に関しては就業規則でも可)にて対象労働者の範囲を明確にする必要があります。
そのため、労使協定等にて対象労働者の範囲を明確化すれば、同じ事業場の異なる部署、あるいは労働者ごとに異なる変形労働時間制を適用することは可能です。
例えば、Aという部署では1年単位の変形労働時間制を利用し、Bという部署では1ヶ月単位の変形労働時間を利用することもできますし、また、同じ1年単位の変形労働時間制を利用するけれども、部署ごとにカレンダーを変更する、ということもできます。
同じ事業場でも適用する変形労働時間制の数だけ届出が必要
ただし、異なる部署や労働者ごとに異なる変形労働時間制を適用する場合、同じ事業場であっても、適用する変形労働時間制ごとに労使協定を結び、労働基準監督署に提出する必要がある点に注意が必要です。
その際、同じ会社の別部署なので、住所や事業所名が同じになる場合があると思いますが、事業所名のところにカッコ書きでA部署、B部署と書いておけば問題ありません。
同様に、部署ごとではなく、労働者ごとに個別に変形労働時間制を利用することもできなくはありませんが、その場合、労働者の数が増えるほど手続きが煩雑になるので、それを上回るメリットがない限り、導入には慎重になった方が良いでしょう。
変形労働時間制はワーク・ライフ・バランスの向上や残業代の削減に繋がる制度ではありますが、導入することで他の労動者の負担が増えてしまっては意味がないからです。