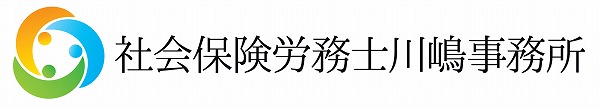懲戒処分とは、会社のルールに違反した労働者に対し、企業秩序を維持する目的で行われる制裁です。
一方で、懲戒処分は労働者にとって重大な不利益となるため、会社が自由に行えるわけでもありません。
この記事では、懲戒処分の種類や法令上の制限、そして懲戒処分を有効なものとするために押さえておくべきポイントについて解説します。
- 懲戒処分の基本的な考え方と制度の位置づけ
- 譴責・減給・出勤停止・懲戒解雇など懲戒処分の種類
- 減給処分に関する労働基準法上の制限
- 懲戒解雇と退職金の関係における注意点
- 懲戒処分が有効と認められるための要件
懲戒処分とは
懲戒処分とは、会社のルールを破った労働者に対し、その制裁として罰を与えるものとなります。
会社のルールを破ること自体、会社の企業秩序を乱す行為ですが、そうした違反者を放置すること自体も、会社の企業秩序を見出すことに繋がるからです。
ただし、会社からすると、懲戒処分は、企業の秩序維持のため不可欠といえる制度ですが、労働者からすると重大な不利益を受けることにもなるため、行為に対する罰のバランスが重要となります。
懲戒の種類
譴責・戒告
譴責とは労働者に対して厳重注意することで、通常、始末書の提出とセットで行われます。
減給
減給とは、本来の賃金から一定の額、賃金を差し引くことをいいます。
減給については、労働基準法にて「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」と上限が決められているので注意が必要です。ここでいう「1回」とは減給対象となる事案1回をいいます。なお、1回の事案の減給を数日に分けて「平均賃金の1日分の半額」を何回も行うこともできません。
一方、減給対象となる事案が複数ある場合、「平均賃金の1日分の半額」を限度とする減給を何度か行うことになりますが、その場合も「総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1」を超えることはできません。
なお、近年では海外での「減給は人権侵害」という風潮を受け、減給処分を行わない会社も増えています。
降格
降格には純粋に、企業の人事として行われるものと制裁として行われるものがあります。
懲戒処分として降格を行う場合、懲戒規定にその定めが必要となります。
出勤停止
出勤停止とは、当該労働者の就労を禁止するものです。
期間については法律上、特に定めはありません。
そのため、期間については会社の裁量となりますが、期間が長すぎると処分が重くなりすぎたり、より重い処分をすることの妨げになったりする場合もあります。
よって、特に理由がないのであれば、7労働日~14労働日、どんなに長くても1か月程度を限度としておくのが良いかと思います。
諭旨退職
諭旨退職とは、労働者に対し会社が退職届の提出を勧告し、退職を求めるものをいいます。会社によっては諭旨解雇という場合もあります。ただ、どちらも法律上定めのある言葉ではないこともあり、定義は人によって曖昧です。
なお、この記事では、勧告に応じた場合の扱いを「退職」としていますが、就業規則の中にはここを「解雇」扱いとしているものもあります(余談になりますが、勧告に応じた場合に解雇することを「諭旨解雇」という規定もあるなど、本当に内容は千差万別)。
ただ、法的に考えた場合、労働者が退職届の提出に応じるかどうかにかかわらず、諭旨解雇は懲戒処分であることにかわりありません。そのため、応じた場合の扱いを「退職」とするか「解雇」とするかにそれほど差があるわけではなかったりします。
それでも、実務上は、解雇という言葉を使うこと自体をそもそも避けたい、できれば、形だけでも自己都合で辞めていってもらいたいと考える会社も多いため、退職扱いとすることが多いようです。
懲戒解雇
懲戒解雇は懲戒処分における極刑として行われるものです。
会社側は、会社の秩序を乱した労働者に対し、即座に懲戒解雇をしたいと考えがちです。しかし、懲戒解雇は極刑ということもあり、その有効性は他の懲戒処分よりも厳しく判断される点に注意が必要です。
イメージとして、懲戒解雇はサッカーのレッドカードなので、よほどの重大な違反でもない限りは一発では出せないと考えてもらうとわかりやすいかと思います。
懲戒解雇と退職金
なお、懲戒解雇の場合、退職金は全額不支給が当たり前と考えられており、実務上もそのように対応している会社も多いと思います。
しかし、もし司法上の争いになって、仮に懲戒解雇の有効性認められたとしても、退職金の全額不支給まで有効と認められるとは限りません。
というのも、退職金は会社に在籍した期間の功労や賃金の後払いと考えられているからです。退職金を全額不支給にするということは、これまでの功労を全部無しにするくらい懲戒解雇の理由が酷くないと釣り合いが取れないわけですね。
そのため、リスクを避けるなら、懲戒解雇であっても、全部とまではいわないまでも一部支給は行った方が良いといえます。
なお、実務的には、懲戒解雇の場合に退職金の一部又は全部を不支給とする場合、その旨を退職金規程等に定めておく必要があります。
懲戒処分の有効性
会社が労働者に対して懲戒処分を行ったとしても、それが客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、無効となります。
では、懲戒処分を有効なものとするには、どういった要件が必要となるのでしょうか
懲戒処分の根拠規定
大前提として、懲戒処分を行う場合、就業規則にその根拠となる規定が必要です。
懲戒事由への該当性
客観的合理的な理由があるかどうかは、就業規則に定めた根拠規定に該当するかどうかが重要となります。
逆にいうと、就業規則に定めのない事由で懲戒処分を行うことは困難ということです。
社会通念上相当かどうか
いくら、理由があるからといって、重すぎる懲戒処分は有効とは認められません。
特に、懲戒処分の極刑である懲戒解雇は、これが厳しく見られます。
相当性については、他のの同一案件と比較して公平な処分となっているかや、手続的な相当性が見られるかなども考慮の対象となります。
就業規則への記載方法
懲戒については、就業規則への記載が必須となっています。
懲戒の規定例については、以下の記事を参考にしていたければと思います。

▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)
こちらの制度は、就業規則にどう定めるかでリスクが変わります。
制度理解だけでなく、自社に合った条文設計や運用まで落とし込むことが重要です。
「不安がある」「何していいかわからない」という方はぜひこちらを!