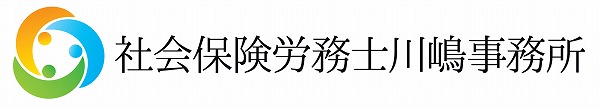日本社会全体の高齢化が進む中、定年を含む高齢者の労務管理は年々その重要性は高まっています。高齢化が進み、労働人口が減少するということは、簡単に新しい労働者を雇うということができないといことだからです。
加えて、政府もまた労働人口の減少の対策として、高齢者の就労を法律や助成金を使って企業に促しています。つまり、定年制度を含む高年齢者の労務管理とは、会社の将来的な成長や存続に加え、法的にも対処が必要な課題となっているわけです。
そのため、この記事では定年に関して、就業規則に定める際にポイントについてまとめていきます。
- 定年を就業規則に定める際に押さえるべき法的ポイント
- 定年年齢・定年退職日の具体的な決め方と実務上の考え方
- 65歳・70歳までの継続雇用制度を設計する際の注意点
- 再雇用時の同一労働同一賃金や嘱託社員就業規則の実務対応
法律・労務管理から見た「定年」
この記事は定年と就業規則の規定について書かれたものです。
法律や労務管理の運用から見た定年について、以下の記事で詳しく解説を行っているのでこちらをどうぞ。
「定年」条文の必要性
定年は就業規則の絶対的必要記載事項である「退職」に関する事項です。
そのため、定年を定めること自体は会社の義務ではないものの、定年を定めている会社では就業規則への定めが必須となります。
「定年」条文作成のポイント
定年退職の年齢
定年退職の年齢については60歳を下回る年齢を定めることはできませんが、60歳以上であれば、何歳としても問題ありません。
そのため65歳や70歳などを定年年齢とすることもできます。
定年退職日の日付
定年退職の退職日をいつとするかは、60歳の誕生日より前にならない限り、会社の裁量の部分となります。
そのため、記事の最後の規定例のように「60歳の誕生日」ではなく、「60歳の誕生日の直後の賃金締切日」や「60歳の誕生日の属する年度の末日」のように、賃金の締切や契約期間からみて切りのいい日を定年退職日とすることも可能です。
65歳までの高年齢者の雇用確保措置をどうするか
65歳までの高年齢者雇用確保措置や、70歳までの高年齢者の就業確保措置については、会社側に様々な選択肢があります。
再雇用による継続雇用制度を選択する場合、同一労働同一賃金に注意
いずれの措置を実施するかは会社の裁量の部分となりますが、一般的には定年退職の際に労働契約を見直すことができる再雇用(定年で一旦退職扱いとし、再度契約を結び直す)を選択する会社が多いようです。
再雇用を行う場合、再雇用後は非正規扱い(嘱託社員などとすることが多い)とすることが一般的ですが、これにより雇用期間が有期となったり、所定労働時間が短くなったりすると、パートタイム・有期雇用労働者法の対象となります。
パートタイム・有期雇用労働者法の対象となるということは「同一労働同一賃金」の対象になるということです。
よって、再雇用によって給与を引き下げる場合、その引き下げにきちんとした理由がないと、同一労働同一賃金に違反する可能性があるので注意する必要があります。
嘱託社員の就業規則を忘れずに作成
定年退職職者を再雇用する場合、当該労働者は非正規扱いになることが多いですが、こうした労働者向けの就業規則(いわゆる嘱託社員就業規則)、正社員の就業規則とは別にきちんと用意しておく必要があります。
嘱託社員と正社員では、手当や賞与、退職金などで異なる扱いをしていることが多いと思いますが、仮に嘱託社員就業規則がないと、正社員の就業規則が適用されてしまい、嘱託社員に払うつもりのなかった手当等を支払わなければならない、ということが起こり得るからです。
定年年齢の延長や定年の廃止を行う場合、人件費に注意
再雇用ではなく、定年年齢を65歳や70歳に引き上げたり、定年自体を廃止するという選択肢ももあります。
ただし、再雇用と違って、こうした措置を実施する場合、定年を理由に賃金を引き下げることは難しいという点はあらかじめ押さえておく必要があります。
いずれにせよ、高年齢者の雇用確保については会社の目的や実態に合った措置を選択すべきです。
65歳以降の雇用
65歳以上70歳までの高年齢者の就業確保については、現行法ではあくまで努力義務です。
そのため、余裕がない、という会社は無理して措置を行う必要がないので、実施するかどうかは会社ごとの判断となります。
65歳以降の継続雇用
なお、65歳以降の継続雇用(再雇用)については、65歳までの継続雇用と異なり、65歳から70歳までの継続雇用については、再雇用するかどうかについて、人事評価の成績など継続雇用の基準を定め、その基準を満たす者のみを再雇用する、ということが可能です。
一方で、会社が恣意的に特定の労働者のみを再雇用とすることは問題があるため、65歳以降も継続雇用を行う場合は65歳前と同じく希望者全員を対象とするか、継続雇用の基準を定め基準を満たす者のみを再雇用とすべきです。
5年ルールと有期の定年後再雇者
有期雇用特別措置法の第二種計画認定
有期雇用労働者の契約期間が通算で5年を超えた場合、有期雇用労働者は、会社に対して無期転換の申出が可能となり、会社はこれを拒否できません。いわゆる5年ルールというものですが、これは有期で雇用される定年後再雇用者であっても同様です。
ただし、会社が有期雇用特別措置法の第二種計画認定を受けている場合、定年後再雇用者は条件を満たしても無期転換の申出をすることはできません。
第二定年を設けることも視野
問題は、この第二種計画認定はあくまで定年退職して再雇用された有期雇用労働者にしか適用されない点です。
そのため、60歳定年の会社が、何らかの理由で60歳以上の人を雇用、その後、通算契約期間が5年を超えて無期転換申出をしてきた場合、会社はこれを拒否できないわけです。
また、有期雇用からの無期転換ではなく、定年以上の年齢の労働者を最初から無期で雇用する場合もあるでしょう。
つまり、「定年で定めた年齢よりも上の年齢の無期雇用労働者」というのは年齢で退職させることができないわけですから、真の意味での終身雇用労働者であり、制度や運用に不備があるとどの会社にも生まれる余地が出てきます。
こうしたことをさけるには、本来の定年とは別に第二定年を設けるなど、就業規則で対策をしておく必要があります。
就業規則「定年」の規定例
第○条(定年)
- 従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日を定年退職日として退職とする。
- 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望した場合で、解雇事由または退職事由に該当しない者については、再度労働契約を締結し直した上で、65歳の誕生日に達するまでを限度として、嘱託社員として継続雇用することがある。
- 嘱託社員としての労働契約は最長1年間の有期雇用契約とし、労働契約書に定める更新基準に則り、更新の有無を判断する。
規定の変更例
定年を設けない場合
第○条(定年)
従業員の定年は設けないものとする。
定年退職の退職日を誕生日直後の賃金締日とする場合
第○条(定年)
- 従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日の直後の賃金締切日を定年退職日として退職とする。
- 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望した場合で、解雇事由または退職事由に該当しない者については、再度労働契約を締結し直した上で、65歳の誕生日に達するまでを限度として、嘱託社員として継続雇用することがある。
- 嘱託社員としての労働契約は最長1年間の有期雇用契約とし、労働契約書に定める更新基準に則り、更新の有無を判断する。
65歳まで継続雇用し、さらに70歳まで希望者を継続雇用する場合
第○条(定年)
- 従業員の定年は満60歳とし、60歳の誕生日を定年退職日として退職とする。
- 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望した場合で、解雇事由または退職事由に該当しない者については、再度労働契約を締結し直した上で、65歳の誕生日に達するまでを限度として、嘱託社員として継続雇用することがある。
- 前項にかかわらず、65歳に達した従業員が希望した場合で、解雇事由または退職事由に該当しない者については、再度労働契約を締結し直した上で、70歳の誕生日に達するまでを限度として、嘱託社員として継続雇用することがある。
- 嘱託社員としての労働契約は最長1年間の有期雇用契約とし、労働契約書に定める更新基準に則り、更新の有無を判断する。
▶ 就業規則の作成・見直しサービスを見る(名古屋の社労士が対応)
社会保険労務士川嶋事務所では、名古屋市および周辺地域の中小企業を中心に、就業規則の作成・改定を行っています。川嶋事務所では、この記事で見た条文を含め、
・会社の実態に合った規程設計
・法改正を見据えたルール作り
・将来のトラブルを防ぐ条文設計
を重視し、あなたの会社に合った就業規則を作成します。